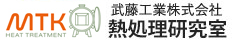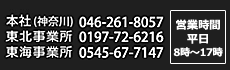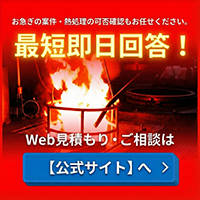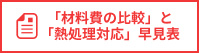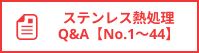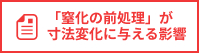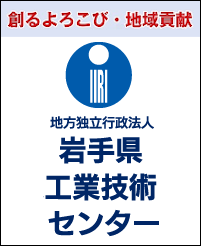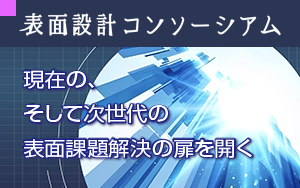焼ならし
「焼ならし」は、鋼を標準状態(常態化)にするための熱処理操作です。加工による組織の不均一を除去し、結晶粒を微細化させ、機械的性質を向上させます。また、機械加工を容易にするため行うこともあります。

焼ならしの目的
- 鋼の内部応力を開放して除去する
- 鋼の結晶粒を小さくする
- 鋼の材質改善を行う(被切削性の向上)
- 圧延などの組成加工で生じた繊維組織を解消する
- 機械的性質の向上
焼ならしの操作
- 加熱……加熱温度:(As または Acm)+50℃ 保持時間:処理前の状態および大きさ、材質により異なり、通常25mm厚につき1~2時間の割合です。この加熱操作により、繊維状組織の消失、過熱組織や鋳造組織の改善が行われます。
- 冷却……静かな大気中で放冷 この放冷操作により結晶粒の微細化とともに、硬く、強く、しかも伸び絞り性もよい微細パーライト(層状)組織が得られます。
焼ならしの方法
通常焼ならし(HNR)(conventional normalizing)
所定の焼ならし温度から常温まで大気中放冷する方法
等温焼ならし(isothermal normalizing)
等温変態曲線の鼻の温度に相当する等温炉(550℃付近)によって等温変態させ、その後は常温まで空冷させる方法です。焼ならし温度から等温炉までの冷却は、熱風冷却により行われる。S-C材、低C合金鋼に対して被削性の向上に有効な処理です。
二段焼ならし(stepped normalizing)
焼ならし温度から火色がなくなる温度(約550℃)まで空冷したあと、ピット又は徐冷箱内で常温までゆっくり徐冷する。構造用鋼材(0.3~0.5%C)にこれを適用すると、初析フェライトが少ない粗層パーライト組織が出来て、伸び、絞りが向上し、強靭性が得られます。また大型の高炭素鋼材(0.6~0.9%C)では白点や内部亀裂の防止に有効です。
ダブル焼きならし(double normalizing)
1回目:高温焼きならし(930℃→空冷)……前組織の改善、低温成分を固溶させる。2回目:低温焼きならし(820℃…Asに近い温度→空冷)……パーライト粒を細かくする。これをくりかえし焼きならし操作を行います。車軸材や低温用の低C鋼の強じん化に用いられ、この場合は焼きならし後に焼きもどし処理が施されます。
焼きならしの適用と効果
| 鋳鋼品 | 均質化(結晶組織の調整、機械的性質の確保) |
| 鍛鋼品 | 均質化(結晶組織の調整、加工の影響除去、機械的性質の確保)(焼きならし、焼きもどし) |
| C鋼 | 被切削性の改善、機械的性質の調整(焼きならし、焼きもどし) |
| 合金鋼 | 焼入れ前処理として施す。この場合は冷却速度を適宜管理する必要がある。 |
| はだ焼き鋼 | 浸炭狂い防止と被切削性改善のため、焼きならし温度は浸炭温度より高い温度を行う。 |
| 過共析鋼 | 網状セメンタイトをなくし、粒状化を容易にする。 |
[ 熱処理 技術情報トップへ戻る ]